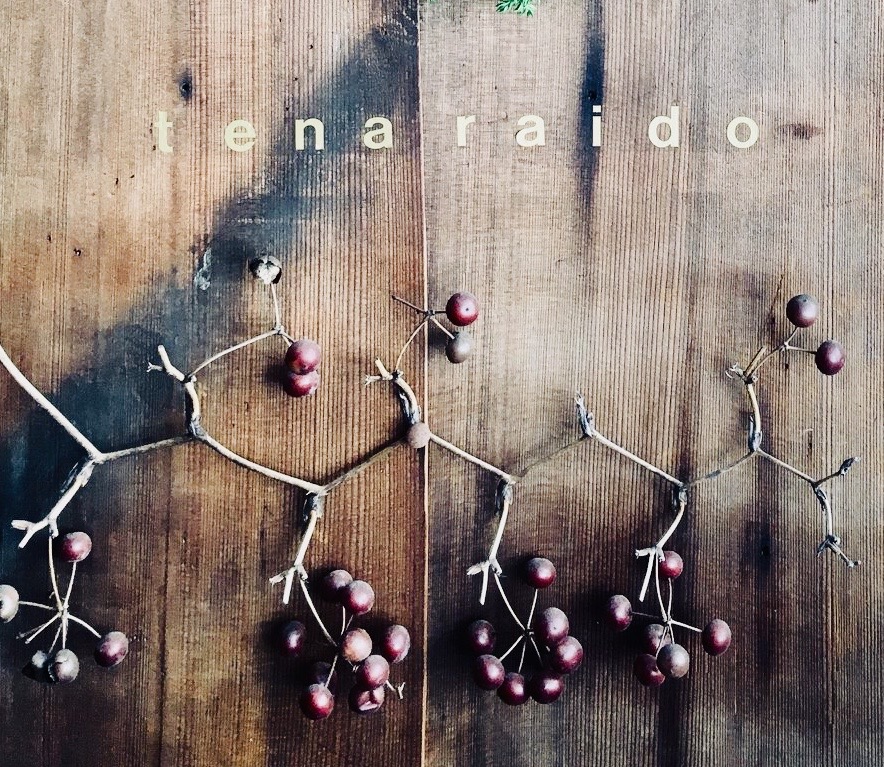【てならい後記】漆をもっと探究する。松本先生の乾漆教室。5回目
こんにちは。てならい堂スタッフのくらです。乾漆教室、今日は5回目です!
前回、ついに型から外しました!外した後錆漆を塗りましたが、今日はそれが乾いたところをやすりでしっかりと削って、整えていきますよ。

とにかくシャカシャカやすりがけ!前回の刷毛や塗った後の形跡があるので、滑らかにする削りの時間です。紙やすりでとことん表面をきれいにしていきます。(削った漆が、砂のようににどんどん出てくる)

乾漆や金継ぎを見ていると、こういう一見目立たないような地道な作業を、大切にていねいにやっていくことが、良い作品の生まれるひみつなんだなあ。。と気付かされます。

しっかりとやすりがけ、出来ているかな~と、先生と細かく確認!
全体をやすりがけできたら、錆漆を足りない部分に塗っていきますよ。
錆漆はうつわの中と外に塗っていくので、塗る順番も気を使います。

形を整えるように錆漆を塗っていくと、全体的に形が厚みや丸みをおびてきて、それぞれのうつわの味が出ていて素敵。最初のころと比べると、形、雰囲気がやっぱりぜんぜん違いますね!

以前高台を付けた部分も、なじませるように整えていきます。

集中!!

しっかりと塗れました。かたちかわいいな~
錆漆を塗ることができたら、次回の削りのために、しっかり乾かします。

次回まで静かに待機して、しっかり乾くのを待つうつわたち。。!
次は<やすりがけ>と、ついに<和紙貼り>の会!ここまで地道にベースを作ってきたので、和紙貼りたのしみですね~!
次回もみなさん、よろしくお願いします◎