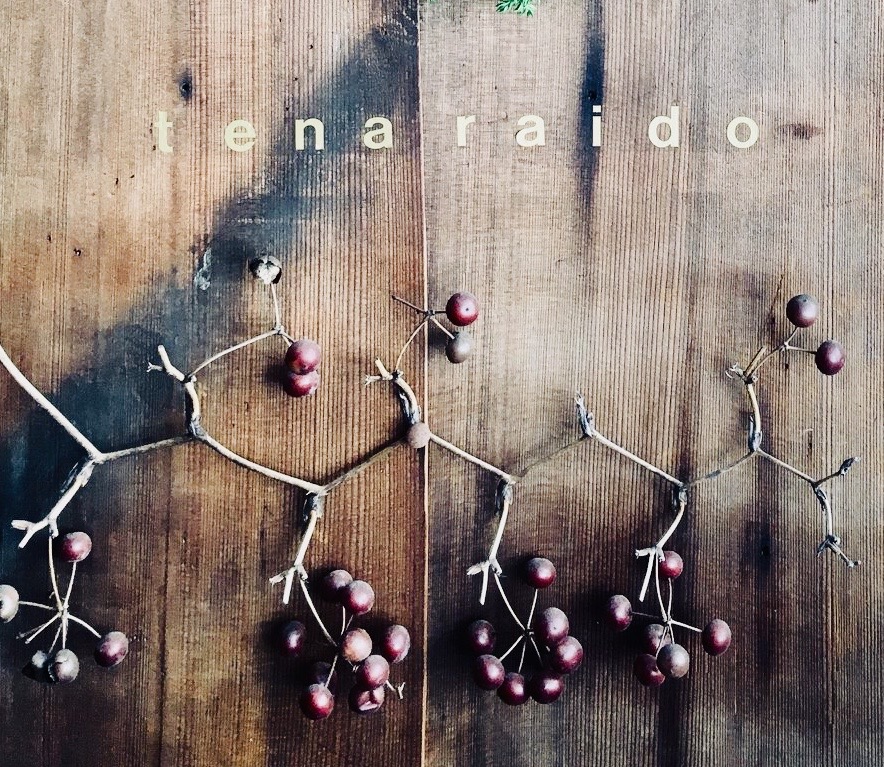【てならい後記】京都の座布団屋さんで、マイ座布団綿入れ体験。《2025年春の会》
こんにちは。店主の中村です。
2年ぶりに京都で座布団の綿入れワークショップです。東京、神奈川、神戸、京都から8組がご参加。5歳のトリオも来てくれました。次の世代につながりますように。

京座布団の秘密をおしえてくれている、高岡屋さん。今年もお世話になりました。
まずは京都で100年を超えて続く、洛中高岡屋さんの座布団づくりについてのお話から。
座布団の前と後ろ、表と裏など、通常は全く気づかない細かな気遣い、その精神性にはっとさせられます。
工房に移動して、あらかじめ選んだ生地にそれぞれに綿を詰めていきます。

この綿をこれから全部いれていきまーす。

重ねていくとこんなボリュームでーす。
丸い形は均等に綿を詰めることが難しく、四角い形は隅っこにも均等に綿を詰めていくことが難しく、どちらの形を選んでも、悲鳴を上げながらの作業となりました。
こんなに多くの綿が入っていること、実際に自分たちで詰められたことに、感動です。

丸く均等にする難しさと、

四角い四隅に押し込む難しさと。
皆さんが体験した大事な座布団は、このあとは職人さんが引き継いで、縫い合わせて配送してもらいます。

目指す正解はかまぼこ型なんですが、どうですか?

お子さんたちに特別ミニミニ座布団体験をプレゼントしてもらいました。ありがとうございます!
参加者の皆さんは、練習用の座布団を借りて、京都ならではの三方綴じと隅っこの房付けを体験。
座布団の隅っこの房って、子供の頃に、なんかいたずらして結んじゃって、怒られた気がしますが、これは中の綿をしっかりと固定する機能的な役割と魔除けの精神性があって、そんなことを子供の頃に知っていたら、あんないたずらしなかったんじゃないかな。とか。

こちらが京都ならではの三方綴じ。

房の意味を聞くと、付けたくなるから不思議。
さらには、綿の入れ口を閉じる”くけ”の技術をこれは、職人さんに披露してもらい、全く縫い目の見えない、仕上がりに皆さんまた驚嘆。
てならい堂で和裁をやってる方は、これは自分でチャレンジしたいかもですね。

くけるところを皆で見学。やりやすい体勢のための、いろんな道具もいいな。
元々はこの辺りは、布団屋さんや座布団屋さんも多かったけれど、だいぶ減ってしまったよう。そんな中で100年続けている高岡屋さんは、やっぱり守るものを守りながらも、何かを変えることにチャレンジして、自分たちの目指すものづくりを続けてきた人たち。
それゆえ、こうやって座布団を深く知ってもらうためのワークショップの開催にもいち早く取り組んできました。今回感じたのは、教え方がまた上手くなっていること。それはお客さんに向き合ってる証拠。きっとこのつくり手さんは、この先も進化を続けられるのだろうなーと思います。
春の京都は、桜にはまだ早かったけれど、気温も上がり、とても良い空気でした。くしゃみはとまりませんでしたが。
次回は11月予定。貴重なワークショップなんですよ。ぜひ、ご予定しておいてください!